
旅行会社のパッケージツアーって儲かるのかな?あるいは儲からないのかな?旅行会社は薄利多売ってよく聞くけど、旅行会社はどのように利益を生んでいくべきなんだろう。
この記事は、そんな疑問に答えます。
・旅行会社の利益の出し方とは?
・旅行会社は儲かる?儲からない?
・旅行会社が儲からない理由とは?
・旅行会社が今後やるべきことは?
こんにちは、ツバサです。
僕自身、旅行業界に長く勤めていて、企画担当者が価格競争だけに注力していることにとても嫌気がさしていました。そこにはマーケティングもアイデアもありません。
旅行会社てるみくらぶが経営破綻したことは記憶に残っているかと思いますが、価格競争の激しい商品に対して莫大な広告費を投入した結果、債務超過となり多額の粉飾決算を行っていました。
旅行会社の一番の醍醐味でもある「旅を通して感動を与える」という本質を失っています。
もちろん戦略的に価格訴求を求めることはあります。
しかし、それだけでは旅行会社も生き残ってはいけません。そして、旅行会社はどのようにして生き残っていくかを考えなければなりません。
この記事では、「旅行会社の利益構造」や「今後やるべきこと」など中心に詳しく解説したいと思います。
旅行会社の利益の出し方とは?

旅行会社の利益はどのように出しているのかというと、一言で言えば「手数料」が利益となります。
例えば、パッケージツアーは航空券、ホテル、送迎、観光ツアーなどを組み合わせて作られますが、それぞれのパーツの金額を足し算して、「手数料」分を上乗せした上でパッケージツアーを販売します。要は「手配代行手数料」みたいなものです。
航空会社やホテルはパッケージツアー用の安いレートを旅行会社に卸しています。これは、旅行会社が利幅を確保できるようにしているためでもあります。
また、国土交通省令で定められた旅行業務取扱料金というものがあり、例えば、レストランを手配したらいくら、レンタカーを手配したらいくらといったように手配代行手数料が決められています。以前、ニュースにもなった旅行に関する相談料金もそれに当たります。
参考資料:JTB 旅行業務取扱料金表
関連記事


旅行会社は儲かる?儲からない?

旅行会社は儲かるのか?儲からないのか?と問われると、僕自身の経験から答えると、
「儲からない」
が答えです。
もちろん、儲かる方法はありますが、なぜ儲からないかと言うと、旅行会社のパッケージツアーの粗利はツアー価格の5%~15%くらいが相場だからです。
10%の粗利が出れば良い方と言ってもよいくらいです。
例えば、フィリピン・セブ旅行3泊4日のツアーが39,800円だったとします。
粗利率が5%であれば、粗利は1,990円のみです。
100名送客しても粗利199,000円のみとなります。
ここから書類発送費用やその他経費を引いたら、一体いくらお金が残るのか。
また、航空券のみの販売の場合は、粗利が500円や1,000円なんていうこともよくあります。
旅行というものは「形のない商品」ですが、実際は航空券やホテル、送迎などを組み込んで作られています。
航空会社から航空券を、ホテルから客室を、送迎会社から送迎を購入した上で旅行商品が成り立っています。
つまり、仕入れの費用にかかる金額が高すぎるのです。
上記の例でいうと、セブ旅行が39,800円で粗利率が5%、粗利1,990円ですが、言い換えると95%が仕入れ価格となり、その額は37,810円もかかっているということです。
これでは儲かりません。
毎年どれくらいの旅行会社が経営不振に陥り倒産しているのかというと、東京商工リサーチの発表によれば、毎年25社以上の旅行会社が倒産しています。
価格訴求や消費者の多様なニーズに対応できない旅行会社が倒産したものを思われます。
参考記事:トラベルボイス
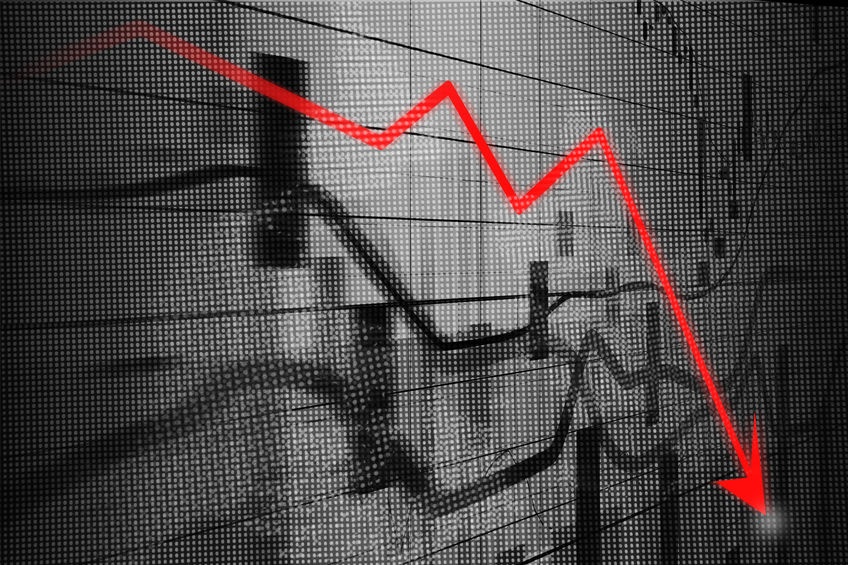
旅行会社が儲からない理由とは?

なぜ旅行会社の利益構造は儲からないのでしょうか。
旅行会社はなぜ価格競争に自ら参入していくのかを詳しく見ていきましょう。
航空会社からのキックバック
旅行会社は長い間、航空会社からのキックバックの恩恵を受けてきました。
キックバックというのは、例えば、2000名分の航空券を発券したら2百万円の払い戻しをする、航空券の発券金額の合計が2億円を超えれば2百万円の払い戻しをするなどのインセンティブ契約から得る払戻金ことをいいます。
このようなキックバックのあるインセンティブ契約については、四半期あるいは半期ごとの契約となっており、旅行会社は航空会社が設定している最低ラインを何としてでも超えようとします。
そのため、旅行会社は四半期が終わる前、あるいは半期が終わる前に、とんでもない価格のツアーを発売して、最後の追い込みをかけるのです。
それが、価格訴求のパッケージツアーです。
僕が今までで一番インパクトのあった価格訴求のパッケージツアーはタイ・バンコク4日間が9800円でした。
このような旅行会社の慣習が、ツアー内容よりも価格のみに目を向けた「利益度外視」のツアー販売の流れを作ってしまいました。
旅行会社としての旅行情報が足りない
旅行会社は、旅行の専門会社であるにも関わらず、旅行情報が足りていません。
これは旅行会社・旅行業界の課題の1つにもなっています。
関連記事

例えば、旅行会社大手のホームページをそれぞれ見てみてください。旅行会社がホームページに掲載している旅行情報はとても一般的でガイドブックと同じような内容です。
情報量に関してはガイドブック以下です。
旅行サイトやブログでも同じような情報を今では簡単に得ることができます。
旅行会社は海外ネットワークがあるはずで、現地視察などから得た旅行情報を市場に情報発信をするべきですが、それができていません。
旅行会社のホームページによっては、国ごとにページを設けており、「現地体験レポート」や「旅日記」のような実際に現地に行って得た情報を掲載しています。
それぞれのウェブページがどれくらい閲覧されたかを示すPV(ページビュー)を調べてみると、閲覧数トップ10の中に必ず現地体験レポートや旅日記のページがランクインしています。
つまり、消費者は日本では手に入らない情報を探しているのです。
旅行情報に関しては、旅行会社はプロとして一番情報量を持っている立場でなければなりません。
「旅行情報量がない=ただの手配代行屋」になってしまいます。
そのため、旅行会社は価格という土俵でしか勝負ができないのです。
旅行商品の差別化を誤解している
旅行会社は現地視察をしているにも関わらず、現地で得た旅行情報に基づいた商品造成ができていません。
ここでいう商品造成というものは「差別化」した商品造成です。
しかし、現地で視察をしたホテルや観光地にかかる費用を単純に足し算をしてパッケージツアーを作っているに過ぎないのです。
消費者の旅行会社離れがあるのは、消費者の視点から旅行会社の商品を見た時に魅力的なものに映っていないからです。
ここ最近では多くの旅行会社が「航空券+ホテル」のみのパッケージツアーを作るようになりました。
これはエクスペディアなどのOTAを意識したものです。航空券とホテルを単純に足し算した旅行は、消費者自身でも作ることができます。
誰でも作れる旅行は大きな利益を生むことはできません。
旅行会社が今後やるべきことは?

旅行会社が今後やっていくべきことは次の3つです。
・顧客目線の商品造成
・価値を考え商品に加える
・リスクを恐れない
顧客目線の商品造成
旅行会社の旅行商品は、旅行会社都合でホテルの選定や観光ルートを決めることが多いです。
ホテルに関しては、キャンセルチャージの条件が緩いホテルやデポジットが不要なホテル、食事やスパなどの特典が出やすいホテルなどを選ぶ傾向があります。
観光ルートに関しては、混載観光をベースにしているため、どれくらい効率よく観光を回せるかを考えています。
しかし、それは旅行会社側のプロダクトアウトにしか過ぎず、顧客目線の商品造成ではありません。
未だに観光の際にお土産屋に強制的に連れて行くようなツアーもあります。
例えば、口コミサイト「トリップアバイザー」のホテルランキング(実際に利用した人が評価したもの)を見ると、どのホテルが実際に評価が高く、人気があるのかがわかります。
しかし、各都市のトップ10のホテルを全てパッケージツアーで商品化している旅行会社は1社もありません。
実際に利用した人が評価しているホテルでさえ使っていないのが現状です。
顧客の旅先でのソリューションとなるものや顧客が良いと思ったもの、必要としているものをツアーに含んでいかなければなりません。
価値を考え商品に加える
最近の旅行会社は「価値」を売ることがとても下手です。
「価値」が何なのかを見つけられていない旅行会社もたくさんあります。
例えば、顧客目線にも繋がりますが、実際に自分が旅行をした時に不便に思うことを解決した旅行サービスが少ないのです。
次の話は、僕自身の実体験です。
この実体験からわかることは、現地滞在中のお客様を考え、想定される滞在中の問題を解決する「価値」を提供したということです。
それにより、顧客満足度も格段に上がるのです。
数年前より旅行会社大手のHISが、インドネシア・バリ島で夏場限定の「Mai Maiサンセットビーチクラブ」を運営をしています。
一度視察をしたことがあるのですが、このサービスは「価値」を提供し、お客様の滞在中の問題解決を行ったサービスでした。
・主要滞在エリアからシャトルバス運行
・綺麗なビーチ
・屋根付きの海の家を設置
・専用トイレ、シャワー、脱衣所、ロッカーを完備
・浮き輪などの用具貸し出し
バリ島の主要滞在エリアのビーチは綺麗ではないため、実際に海に入る気にはなれません。
最近ではバリ島のビーチのゴミ問題も大きな話題となりました。
しかし、このサービスで使っているビーチはとても綺麗で、ビーチ滞在中の問題解決を含んだ素晴らしいサービスだと思いました。
次の空撮写真は、HISが「Mai Maiサンセットビーチクラブ」で使用しているビーチです。バリ島とは思えない綺麗なビーチです。

このHISの例は資金力があるため実現できたことかもしれません。
このような価値を探して、具現化することは時間も労力もかかりますが、旅行会社はこのような価値を探さなければならず、価値を売らないと利幅を増やすことはできません。
リスクを恐れない
日本の旅行会社は、まず一言目に「リスク」という言葉を口にします。
これは、「仕入れ」の場面で度々聞く言葉です。
世界から見て日本の旅行会社は次のように思われています。
・無料特典をすぐに求める
・販売目標の数を約束しない
・料金交渉が激しい
「仕入れ」の場面では、旅行会社側もサプライヤー側も「WIN-WIN(ウィンウィン)」にならなければなりません。
本来仕入れというものは、「これだけの数を送るから○○が欲しい」といったように双方がリスクを取った上で交渉をしなければなりません。
しかしながら、日本の旅行会社は販売目標の数を約束しないにも関わらず、無料特典を出して欲しい、料金の割引が欲しいとホテルなどの取引先に求めます。
ホテルなどの取引先が「何人送客してくれますか?」「何部屋販売してくれますか?」と質問をすると、日本の旅行会社は「それはわらかない」「何部屋販売できるかは約束できない」とすぐに自分側のリスクの話を口にします。
これでは、良い旅行素材も良い料金も仕入れることができません。
僕が仕入れに携わっていた際は、「半年で500ルームナイト販売します」「通年で1000名送ります」などを必ず伝え、交渉に当たっていました。
数を約束することで原価を下げれることも多々あり、利幅を増やすことができるのです。
利幅を増やすためには、数を約束して仕入れをしなければなりません。
固定費を減らす
利益を増やすには固定費を減らさなければなりません。
特に人件費は非常に大きな割合を占めます。
実際、新型コロナの影響で販売スタッフを多く抱える旅行代理店は苦境に立たされています。
特に中小企業で数十人規模のところは非常に苦しいでしょう。
今後の旅行会社の在り方としては、旅行の販売スタッフは業務委託契約にして自社でスタッフを抱え込まないことが望ましいです。
それにより、旅行会社側は人件費や社会保険料などの固定費を減らすことができ、販売スタッフ側は歩合による給料増及び副業にて複数の収入源を持つことも可能です。
以上となります。
旅行会社がなぜ薄利多売なのかがわかりましたか?
今のままでは体力の消耗戦です。単純なスケルトンツアーや一般的な観光ツアーを販売している旅行会社は、どんどん利幅が減ってしまい、生き残る道がなくなるでしょう。
それでは、良い一日を!

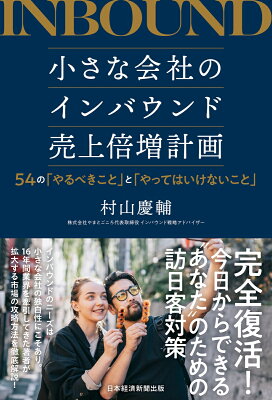


自社の独自性や唯一性を消費者に届け、理解してもらうこと。